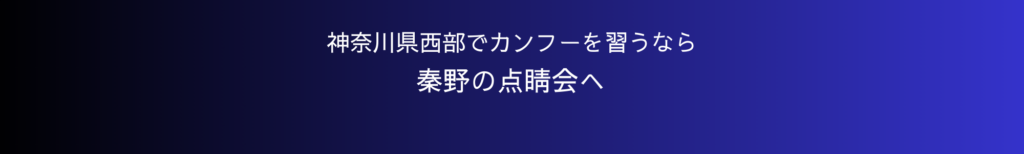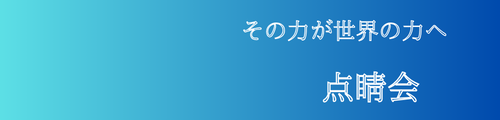長拳技能検定4級攻略ガイド|失敗しやすい動作と合格のポイント
長拳技能検定4級では、転頭・五つの歩型、そして入門長拳が技術面の柱となります。
長拳と言えばスピードやパワーにあふれた華々しい印象がありますが、検定試験に必要なのはもっと違った要素です。
4級試験で大切なのは、スピードや力強さよりも「正しい形の理解」と「安定した表現」です。
この記事では、それぞれの技術ポイントと、受験者が特につまずきやすい点を整理して解説します。
転頭 ― 失敗は少ないが、正確さを意識
転頭(ジュアントウ)は頭部を左右に素早く回す動作です。危険に反応する意味を持ち、目線も重要です。
多くの場合、足を肩幅に開き両手を腰に当て、号令にあわせて一斉に右、正面、左、正面…と90度ずつの転頭を繰り返します。
※180度の転頭は、通常テストに出ません。
よくある失敗
・頭が水平でなく、傾いたりのけぞったりする
・定位置まで回しきれない
・肩や胴体までつられて動く
・目が泳いで対象を捉えられていない
試験では、ここで大きな減点になることは少なく、普通に右や左に振り向ければ合格は可能です。
ただし、姿勢をキープし目線を定めるだけで、一気に見栄えが良くなります。
練習法
鏡に横向きで立ち、腰と肩を固定したまま頭だけを回し、自分の姿を確認する
誰かに手を叩いてもらい、合図で瞬時に振り向く練習で、キレの良さをつかむ
「素早さを意識」し「頭を回す」——これができれば4級としては十分です。
五つの歩型 ― 落ち着いて、形をはっきり見せる

歩型(ブーシン)は、弓歩・馬歩・仆歩・虚歩・歇歩の5種類。
このうち馬歩を除き、左右を示す必要があります。
共通の注意点
・名称は中国語で覚える(左右の区別も正しく)
・弓歩と仆歩、また虚歩(xubu)と歇歩(xiebu)などのように、動作や名前が似たものを混同しない
・低さより正確さを優先
各歩型の傾向と失敗例

弓歩:後脚が十分に伸びず緩んでいることが多い(太極拳の弓歩に慣れた受験者に多いミス)/前脚の膝がつま先を越えてしまうのも減点対象/稀に前足のつま先が外に開いている
馬歩:八字脚(両つま先が少しでも外に開いてしまう形)になりやすい/膝の出過ぎも見られる
仆歩:左右が分からない
仆腿(伸ばした足)の足の裏が浮いてしまう/仆腿のつま先が里扣せず(内に入らず)、外に向かってしまう/仆腿の膝が緩んでいる
蹲腿(しゃがんだ足)のかかとが浮いている
→膝の故障などで高く姿勢をとること自体は問題ないが、その結果弓歩との区別がつかなくなるケースもある。
虚歩:歇歩と混同する/前足に体重をかけすぎる/ジュニアは厳密に行うのが安心/中高年は無理のない範囲で良い
歇歩:ぐらつく/後ろ脚の膝が床に着いている/足の組み方が緩く、後ろ足の膝が、前足のつま先より中に引っ込み過ぎている
確認と対策

まず、名称と左右の区別をしっかり覚えておきましょう。馬歩には左右はありません。仆歩は伸ばした足で、他は前足で左右を区別します。
各動作の要領もテキストにありますから、教室の先生に習うだけでなく、自分でも知識として把握しておきます。
低さは各々のできる程度で大丈夫です。
虚歩は、低い姿勢のジュニアは虚腿がかなり内股になりますが、高い姿勢の中高年受験者は、護裆(股を守る)の意識を持ってやや内向きにするか、あるいは普通に膝を前に向けておきます。
ジュニアのようにと、意図的に前足を内股にする必要はありません。
歇歩のぐらつきは、多くの場合、後ろ足に体重をかけてしまっている為に起こります。この歩型では、前足の大腿部と腹を密着させ、そのまま重心は前足で支えます。つぶれにならないよう、胸から上は力をこめて張る事ができれば上出来です。
また、稀に前足のつま先が内に向いているためにぐらつく受験者もあります。歇歩の前足は外展(外向き)が正しい向きですから、テキストで確認をしましょう。
入門長拳 ― とにかく通しきる
入門長拳では、「最後まで通せるかどうか」が最大のチェックポイントです。
必須条件
二か所四回の発声は必ず行う
動作を仮に一人でもできること
4級合否判定の基準は「それなり」にできること。では「それなり」とは?

4級合否判定の基準は「それなりにできること」。
つまり 入門長拳を最後まで通せれば合格レベル と考えて良いでしょう。
ただし「いい加減でOK」という意味ではありません。
チェックされる点
・6級、5級で学んだ基礎(衝拳・弾腿・双推掌・震脚など)が維持できているか
・入門長拳に含まれる新しい技術(搂・撩・切・架・压・按など)をある程度理解できているか
・新しい大きな動作(拍脚・烏龍盤打など)が「まあまあ分かる」程度で表現できるか
3級以上のような厳密さは不要で、教室で習ったとおりに通せれば合格ラインです。
完璧でなくても「弾腿と呼べる形」「拍脚と言えるだろう」程度で良いのです。
入門長拳、細部の確認
ここでは試験に主眼をおいた細部の確認だけをしましょう。
(入門長拳の動作を一から細かく学びたい方は入門長拳前編・入門長拳後編の記事をご覧ください。)

拍脚は、参加者によってやり方の違いが多く見られます。
着地の際に 「つど併歩に戻る」か、「前点歩のままにする」かは、人によって異なります。
周りと自分のやり方が違っても、あまり気にする必要はありません。
本来の 連続進歩拍脚 はスピードを重視するため、試合などでは併歩を挟まずに行います。
公式模範演武やテキストでも併歩に戻してはいません。
しかし、この套路は「入門用」として、大人数で号令に合わせて行うことが多いため、やや高度な前点歩で停止する方法よりも、きちんと併歩に戻るやり方が普及しています。
したがって、検定時に拍脚の着地で併歩に戻っても、不合格の対象にはなりません。
また一方で、転身上勾拳で上腕をおさえる人が見受けられますが、ここは前腕をおさえるのが一般的です。
上腕をおさえていると、間違っていると指摘を受けたりしますから、当日慌てないように、事前に修正しておきましょう。
入門長拳の各動作の中国語名称は、テストには出ませんが、会場では当たり前のように使われるかもしれません。
長拳技能検定4級、技術確認まとめ ― 細部を押さえれば合格は近い
4級技術試験で大切なのは、華やかさよりも正確さと落ち着きです。
入門長拳をしっかり通すことができれば、大人でも子どもでも合格率は非常に高い試験です。
事前講習で必ず確認してもらえる細部——転頭のコツ、歩型の区別——を押さえ、落ち着いて臨みましょう。
皆さんの合格をお祈りしています!
※試験の内容、採点の基準等は、この記事に関わらず、必ず最新のJWTF公式実施要綱でご確認ください。
また、この記事では合格のための最小限の説明になっています。入門長拳の動作をもっと知りたい方は「入門長拳・前編」「入門長拳・後編」をご覧ください。(
執筆者 石川 まな (カンフーチーム 点睛会 代表)
関連記事
長拳技能検定4級の全体像と試験の流れ|受験前に知っておきたいポイント