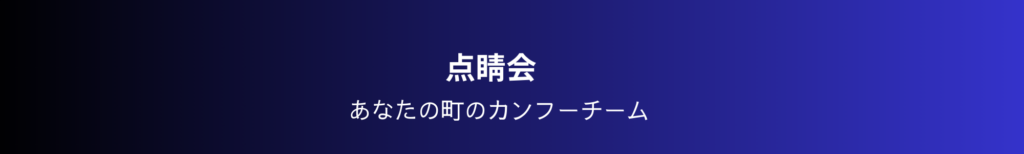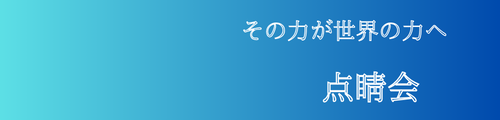長拳技能検定、事前講習会のお話

長拳技能検定試験に向けて、みなさん準備は順調に進んでいるでしょうか?
この記事では、これから挑戦しようとしている方々に向けて、事前講習の大切さや心構えについて、自分のちょっとした体験談も交えながらお話ししたいと思います。
事前講習会には、必ず出ましょう
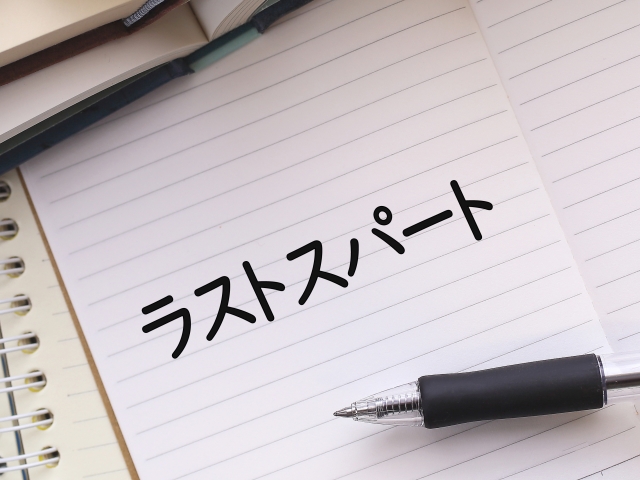
ときどき、「事前講習に出た方がいいのかな?」と迷っている人を見かけますが、これはもう迷わず「出る」の一択です。
参加するだけで、検定本番がぐっとやりやすくなります。
長拳技能検定では、いきなり知らないことを問われるようなことは基本的にありません。
出題される内容は、事前講習でしっかり説明してもらえるようにできているのです。
じつは筆者が受けたときは、何も知らずに会場に行ってしまいました。
「申し込みとか手続きとか、全部こっちでやっておくから、当日行ってね」と友人に言われ、会場に着いてから「え? テキストって何?」「型って何かあるの?」と驚愕。
あわてて、近くにいた小学生に「規定套路やって見せてくれる?」と頼み、全集中して3つだけ覚えるという情けないスタートでした。
そんな状態でも、事前講習で「これが出ますよ」と丁寧に教えてもらえたので、規定套路だけでなく、基本功も細部まで理解でき、事なきを得たのでした。
今思えば神奈川の講習会は、検定初心者に優しく、完璧な内容でした。
とはいえ、さすがに筆者のように“完全に白紙の状態”で行くのはおすすめできません。
できるだけ前もって、試験内容を自分で確認し、練習しておきましょう。その上で更に講習会に参加するのが一番です。
講習で戸惑いやすいポイント

事前講習では、試験に出る内容をすべて教えてもらえます。
ただ、参加してみると「えっ?」と戸惑う場面に出くわす人も少なくありません。
よくあるのは、「普段自分が教室でやっている方法」と、「講習会で教わる方法」が違っているというケース。実際、検定準備をしている方からもよく質問を受けます。
たとえば、こんなことが起きます:
準備体操で見たこともない動きを指示される
自分は中高年だけど、「ヤートエ」で周囲の子ども達がつま先をおでこにくっつけているので焦る
拍脚のやり方がみんな違う
虚歩と歇歩など、専門用語が先生によって聞き分けられない
弓歩衝拳の手の構えが「格肘」だと思っていたのに、搂でやる人もいる
こんなふうに、套路以外の準備体操や基本功の細かい部分では、教室や先生ごとにやり方が異なることがあるのです。
自分だけ違う動きをしていると、「これ大丈夫かな…」と急に不安になりますが、ご安心を。
試験官の先生は、課題動作を判定基準をもとに採点しています。
課題となる動作が基準を満たしてるかを見ているのであって、その他の動きの差異に関しては、それが長拳として正しい範囲におさまっているならば、合否に影響することはまずありません。
不安な方は、検定試験を実施している日本武術太極拳連盟の、公式テキスト※1の通りにしましょう。
また、講習会で分からない点があれば、その場で先生に聞いてみるのが一番確実です。
指摘されたところをこなせるように
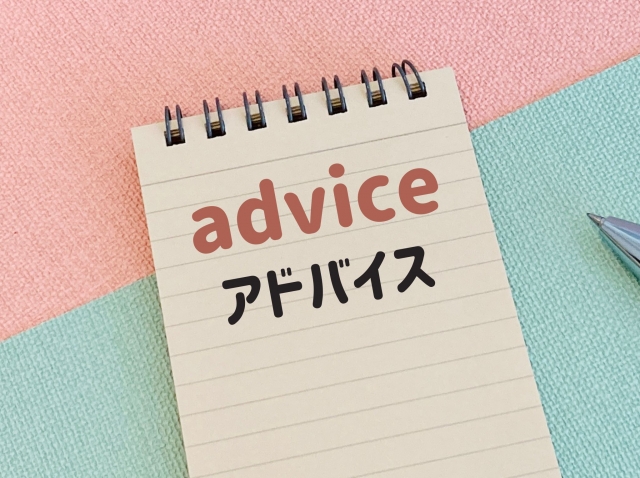
講習会では、全体に向けた動作の説明だけでなく、先生が個別にアドバイスをくれることもあります。
これは問題点を知る大切なチャンスです。
たとえば、弾腿の動きで「曲げ伸ばしが甘いですよ」と言われたら、自分ではできているつもりでも、客観的にはまだ改善の余地があるのかもしれません。
また、たとえば太極拳の教室で「掌はやわらかく保つ」ことを一貫していても、長拳の講習で「親指を曲げて、掌全体を張る」などと指摘された場合、試験に際しては言われた通りこなせるように注意します。
講師の先生の指摘を心にとめて修正し、試験時にそこをクリアーして見せようとすることは、合格のためのコツです。
級が上がると講習のスタイルも変わる
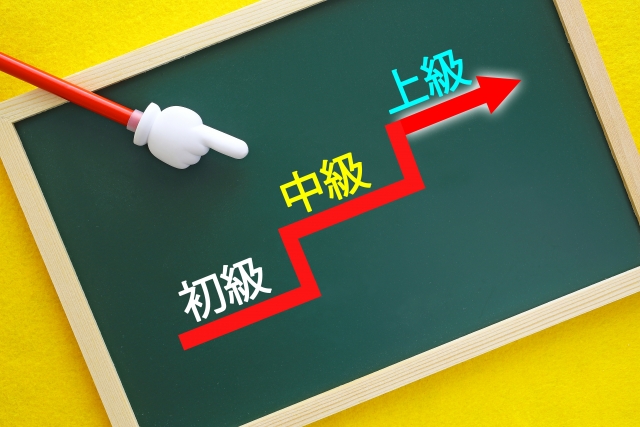
ここでひとつ注意点です。
事前講習では「試験に出るものはすべて教えてもらえる」と言いましたが、上級になってくるとその様子が少し変わってきます。
上の級に進むほど、「これまでに合格した級の動作はできていて当然」という前提のもと、講習が進んでいくようになります。
そのため、講習では当日の課題については説明されますが、過去に学んだ内容についてはスルーされることもあります。
技能検定は、ひとつひとつ積み重ねていく積み木のようなもの。
毎回の試験範囲だけを見ていても、そこまでの内容がしっかり身についていなければ合格は難しくなります。
これは特に套路試験で顕著です。
たとえば2級を受けるとき、事前講習で衝拳や転頭の説明がなかったとしても、套路試験中にそれらができなければ、初級長拳の完成度として不十分と見なされてしまう可能性があります。
つまり、上に進むほど「できていて当然」とされる部分が増えるのです。
長拳技能検定試験、事前講習会のまとめ
事前講習会は、受検者に合格してもらうために設けられています。
試験のポイントを丁寧に教えてもらえるだけでなく、参加者の長所や、今後の課題についても前向きなアドバイスをもらえる機会です。
暑い時期の試験と講習は少し大変かもしれませんが、ぜひ積極的に参加し、学びを楽しんでください。
みなさんの挑戦を、心から応援しています。
※試験の内容、採点の基準等は、この記事に関わらず、必ずJWTF公式の実施要綱でご確認ください。
執筆者 石川 まな (カンフーチーム 点睛会 代表)
補足
※1(社)日本武術太極拳連盟編,『普及用長拳』, (社)日本武術太極拳連盟,1998